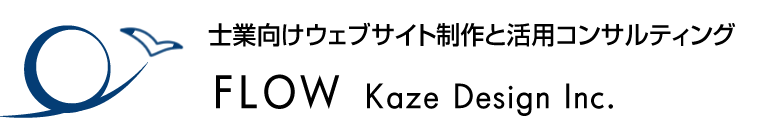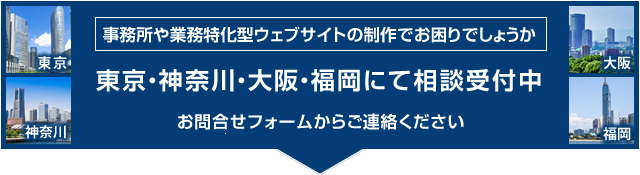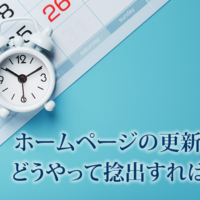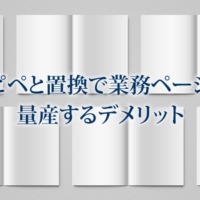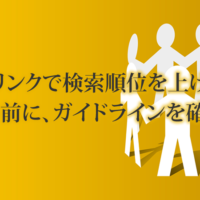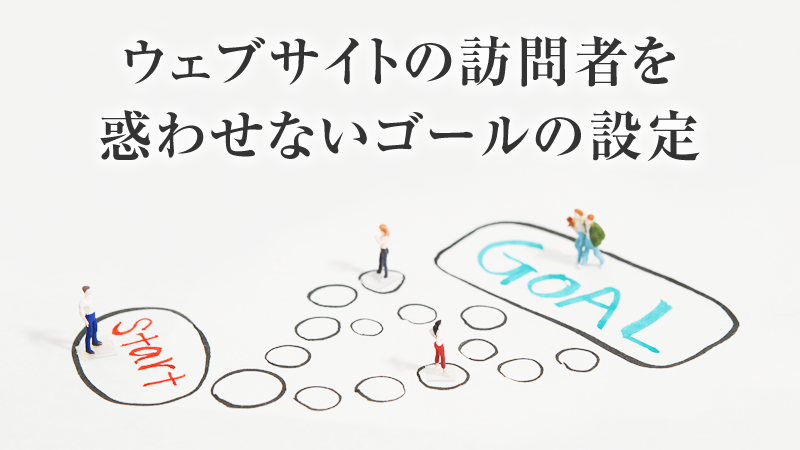
ウェブサイト(ホームページ)は、訪問者に対して最終的に起こしてもらいたいアクション、つまりウェブサイトのゴールを明確に設定しておかないと、当たり前ですが期待するほどの結果が得られない事態に陥ります。
どのようなことに気をつけて、ウェブサイトのゴールを設定していけばよいでしょうか。
ゴールは1つに絞ったほうが反応を得やすい
前回の記事で触れたウェブサイトのターゲットを明確にすることと類似しますが、ウェブサイトの最終的なゴール設定についても、絞れば絞るだけ明確になり、反応を得やすくなります。
より具体的には、ウェブサイトの制作段階において、電話なら電話、メールならメール、あるいはそれより一段階手前の資料請求や無料メールマガジン登録を目的とするならそれのみにゴールを絞って、配置するコンテンツの流れをできるだけ1つのゴールのみに導いていくような構成を考えます。
主とするゴールを明確にする
士業事務所においては、電話での問い合わせ、またはメールでの問い合わせを目的にウェブサイトを制作することがほとんどでしょう。(LINEなど別のツールに誘導するケースもあるかもしれませんが、ここではおいておきます)。
よって通常、電話かメールのいずれかをゴールとして設定することになります。
これを「電話での問い合わせもほしいけど、メールが便利な人もいるだろうから、両方とも目立たせるようにバナーやボタンを配置しよう。ついでに資料の請求がしたい人もいるだろうから、バナーを張って誘導しよう」といった具合にすべてのゴールを目立たせてしまうと、訪問者の側にはどれが主流であるか迷いが生じてしまいます。
もちろん、電話問い合わせをメインに据える場合でも、便宜上メールでの問い合わせを希望する訪問者もいます。
そのため、電話優先ならお問い合わせフォームを絶対に置くなということにはなりません。あくまでどちらのゴールを主としているのか、士業事務所の側で明確に認識して、そちらが活性化するように目立たせなければ迷いが生じる、結果として反応率が悪くなるという意味です。
あれもこれも欲張らない
ウェブサイトのゴールについては、電話やメールのほかに、他のウェブサイトとのリンクが悪いほうに影響して邪魔をすることもあります。
「この業務ではなく、訪問者はもしかしたらあっちの業務にも興味があるかもしれない。念のため別の業務を専門に取り扱っているウェブサイトも、分かりやす何個か紹介してリンクを張っておこう」
取り扱う業務のウェブサイト同士を脈絡なく連携させて、訪問者を混乱に陥れて、最終的には別の業務特化型ウェブサイトに移動した先で訪問者が離脱してしまう構造を、自ら作り出しているわけです。
まさに「二兎を追う者、一途をも得ず」の実現ですが、実は士業事務所ウェブサイトにおいてはかなり頻繁に見受けられるケースです。
ウェブサイト公開後に設定したゴールの有効性を確認する
ウェブサイトを制作していく過程で、最終的にそのウェブサイトを訪問した人にどんなアクションを起こしてもらうのかというゴールの設定を意識することは大事ですが、ウェブサイトの完成・公開後においても、お問い合わせの電話なら電話、メールならメールと、設定したゴールが有効に機能しているのかデータから確認しておきたいところです。

訪問者に対する受電(あるいはメール問い合わせ)率
まず確認するのは、ウェブサイトに訪問している人数に対して、どれだけの割合の人がゴールに到達しているか、つまり訪問者全体に占める受電やメール問い合わせの率です。
これは何パーセント以上なら合格といった絶対的な基準はありません。基本は1か月ごとに自分のウェブサイトの反応率を計算して、それが前月や前年同月と比較して上がっているのか下がっているのか、相対的に確認する作業になります。
これらの比較は、ウェブサイトに対してどのような修正・改善を加えたのか、その変更ログと照らし合わせるとより効果的です。
ウェブサイトを訪問したら最初に目に飛び込んでくるヘッダーに配置された画像を変更した場合など、比較的大きな修正であれば、それだけでゴールまで至る訪問者の率が目に見えて変わることもあるでしょう。
ただし、ウェブサイトに変更を加えた後の反応率の変更については、短期的・短絡的に結びつけないように意識することも大事です。たとえばGoogleのアルゴリズムのアップデートが行われて一定の検索ワードの順変動が起こったことが要因であるにもかかわらず、「このヘッダー画像を入れたから電話が急に多くなった!」と勘違いしてしまうと、反応率の向上には関係なかった施策を次々と導入してしまう結果に結びつきかねないからです。
訪問者が少ないサイト公開直後はリスティング広告で反応率を探る
一定の訪問者がゴールまで達するウェブサイトに仕上がっているかどうかは、ウェブサイト立ち上げ当初であれば訪問者の数自体が少ないため、数か月の期間よくわからない状態が続くこともあります。
このようなときはリスティング広告(検索連動型広告)を活用して、もっとも基本的なワードである程度の訪問者を呼び込んでしまうのも一つの手になります。
お金で時間を買ってしまうことで、早めに対策を練ってウェブサイトの修正を図るということができます。
受電(メール問い合わせ)に占める依頼前提率
反応率を確認するときにしっかりと押さえておきたいのは、受電(あるいは問い合わせメール)全体に占める、依頼を前提とする受電(あるいはメール)の率です。ウェブサイトを業務受任のために設置する、つまり集客を目的としたウェブサイトであれば、ここが非常に大事なポイントになります。
アクセス数に対する受電(メール問い合わせ)率がいくら高くても、そのほとんどが単なる質問や、本来意図するものとは異なる問い合わせなどでは、営業のためにウェブサイトを開設した意味がありません。
上の記事で触れた内容と被りますが、依頼を前提としないお問い合わせの率が極端に高いときは、ウェブサイト内のコンテンツやお問い合わせバナー直前の文言などを変更して、修正を図る必要があります。
この調整を行わずに、ウェブサイトからの効果的な集客は難しいです。
ウェブサイトの変更ログとアクセス解析データの活用
以上のように、ウェブサイトの制作過程においては特定のゴールを設定すること、公開後は訪問者がゴールまで到達した割合をしっかり確認・把握して、ウェブサイトの改善に活かすことが大事です。
特にウェブサイトを公開した後、日々の修正や変更はデータと照らし合わせずに、なんとなく感覚で行ってしまう士業事務所さんも多いと思います。
到達率を検討する場面に限らず、ウェブサイトの修正・変更のログ(面倒な場合はメモ帳に日付と内容をなぐり書きする程度で構いません)とアクセス解析(これも面倒なときは、公開直後にGoogle Analyticsを設置して放置で構いません)は、後日様々な場面で役立つ可能性があります。
使うかどうか分からないときでも、できるだけアクセス解析を導入し、データだけは取れている状態にしておくことをおすすめします。
関連性の高い記事
IWAMOTO
最新記事 by IWAMOTO (全て見る)
- 2024年G. W.期間中の休業日について - 2024年4月26日
- 【制作事例】東京都世田谷区の法律事務所様(総合サイト) - 2023年11月13日
- 【制作事例】宮城県仙台市の税理士法人様(総合サイト) - 2023年11月13日