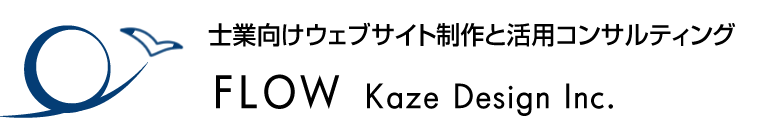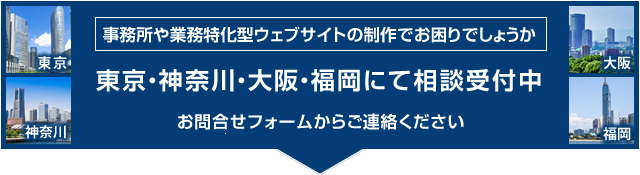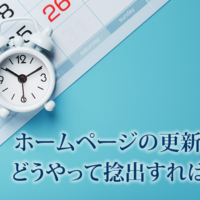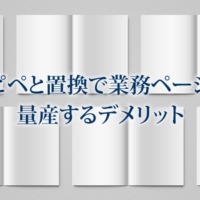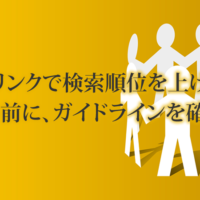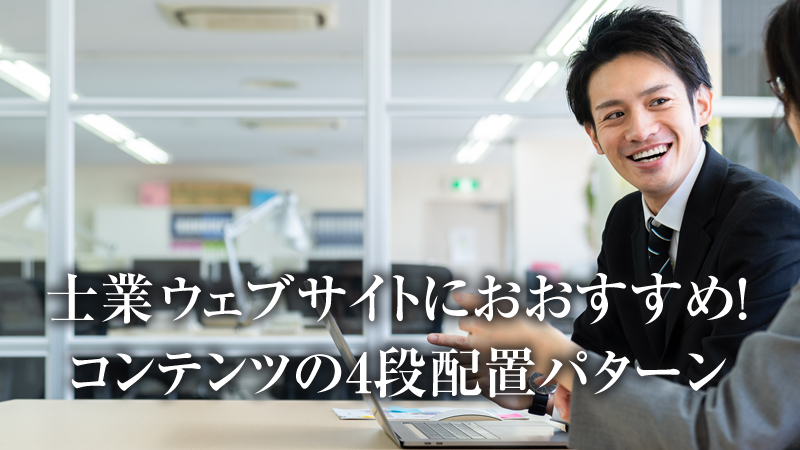
士業事務所のウェブサイト制作において、全体の「流れ」を意識することは非常に大事です。
ウェブサイト内部のコンテンツの配置が効果的な流れになっているかどうかによって、最終的な反応率が大きく変わってくるためです。
ウェブ上の流れは、サイト外部から内部への流れと、内部に至った後の流れに分かれますが、今回はそのうち主に後者、ウェブサイト内部の流れであるコンテンツの配置順について基本的な考え方を紹介します。
士業といっても資格や取扱業務によってはウェブサイトへ以下のパターンを当てはめにくいものもありますが、はじめてウェブサイトを作るという方は、ひとつの考え方として参考になると思います。
※特に、情報提供型のページよりも士業事務所で取り扱う業務を紹介する「業務案内型ページ」で使えるパターンです。
検索サイトからの入口部分にはスムーズな導入が必要
まず最初に意識したいのは、士業事務所のウェブサイトの訪問者は登録したお気に入り・ブックマーク経由ではなくGoogleやYahoo!などの検索サイトを経由してウェブサイトに訪問することが圧倒的であるということです。
そして、検索サイトで何かを調べる人のほとんどは
- 何らかの悩みを解決したい
- 新たなことに取り組みたい
この2つのどちらかを頭の中に思い浮かべて、いくつかのウェブサイトを比較しながらネット上を移動しています。
訪問者の悩みや希望に合わせた導入部を考える
そのためウェブサイトを訪問した際、最初に目に飛び込んでくるエリアは、訪問者への招待状として機能する大事な部分といえます。
そこで、競合するウェブサイトから一歩抜け出すために、検索する人の頭の中(およびそれが具体化された検索語句)を想像して、士業ウェブサイト冒頭の内容を訪問者の頭の中に浮かんでいるキーワードと合わせるように構成します。
訪問者の悩みや希望に合わせるほど、「ここが探していたウェブサイトだ」という合致感を抱いてもらいやすく、結果としてウェブサイトにとどまってくれる可能性が高まるためです。
初対面ですぐ営業活動を行うとサイト訪問者は面食らう
逆に言えば、士業側のサービスや事務所の特徴などは、できるかぎり後回しです。
自分の立場から考えるほうがキャッチコピーを思いつきやすいので、士業事務所ではつい「○○はお任せください!」「○○は専門の当事務所へ!」という主張型のキャッチコピーでウェブサイトを作ってしまいがちです。
しかし、こういった営業行為はWebサイト冒頭では極力出さないようにしてください。
検索からの流れを考えれば想像しやすいと思いますが、何らかの悩みや希望について調べている人は、頭の中が「これはどうしたら解決できるのかな」「これって、どうやったらできるのかな?」という状態です。ここで、まだ見ず知らずの士業さんから唐突に「私にお任せください!」「いますぐお電話!」と言われても、通常、面食らってしまう人のほうがほとんどでしょう。「ていうか、あんた誰?」状態ですよね。
※念のためお断りしておきますが、「お任せください!」系が絶対にダメというわけではありません。実績による差別化や、特定業務をさらに区分して特徴を訴求する場合、あるいはリスティング広告と組み合わせて急ぎの対応を希望する訪問者に対しては、先に主張してしまうほうが早いこともあります。お任せください型のキャッチコピーが作りやすいからと、何の考えもなしに使ってしまうのがダメなのです。
士業ウェブサイトへおすすめするコンテンツ配置パターン
以上を前提に、行政書士、社会保険労務士、税理士など士業のウェブサイトを制作する際、おすすめのコンテンツ配置パターンは以下のようなものになります。

第一段階を実践している士業事務所は多いですが、そこから第四段階に直結で流してしまうパターンがほとんどです。これだと、効果はそれほど期待できません。
理由は、せっかく冒頭の招待(導入)部分は機能しかけたものの、その直後で結局士業事務所の営業が唐突に展開されてしまい、訪問者との関係を築くことができないからです。第一段階からすぐ主張へ繋げず、ここではまだ我慢して溜めが必要です。
この辺は、名刺交換をしただけの人に「これ任せて!僕に仕事ください!」と言ってはいけないのと同じイメージですです。
訪問者の側で生じている具体的な問題点の抽出が重要
そこで大事になってくるのが、第一段階から第二段階への流れ、そして第二段階から第三段階への流れです。
まず、第一段階で大きなくくりとして「○○でお悩みでしょうか?」「○○したい!と思いませんか」といった訪問者側の悩みや希望をキャッチコピーとして配置し、第二段階ではその悩みや希望があるからこそ直面することになる、具体的な問題点をもう一段階掘り下げて配置します。
そして具体化した悩みや希望に対して、士業側で対応可能なことを第三段階で応えるような流れをつくります。
第二段階は訪問者の思いと士業の主張の連結器
ここでもっとも重視しなければならないのは、訪問者側の考えと士業の主張の連結器となる、第二段階の部分です。
第二段階で具体的な問題点を抽出して、それに対してフォローするかたちで第三段階の士業側の主張を持ってくるからこそ、「なるほど」「そうなんだよね」「わかってるね」という共感を持ってもらいやすくなるからです。
また第二段階は、訪問者のより具体的な問題が立ち現れる意味でも重要な部分です。にもかかわらず、ここにほとんど触れていないウェブサイトが多いため、競合サイトが乱立する業務ほど力を入れて差別化を図りたいところです。
招待、共感の後に士業側の自己主張
第一段階で訪問者の頭の中とズレの少ない導入(ウェブサイトへのソフトランディング)、第二段階で具体的な問題の抽出、そして第三段階で士業側のフォローを入れることによって、ようやくウェブサイトの訪問者に対して、士業が本来主張したかった内容に目を通してもらいやすい環境を整えることができました。
ここに至って、最後の第四段階として士業側のサービス提供やお問い合わせへの誘導などを配置することになります。
自己主張ではなく相手の気持ちが先
以上を簡潔にまとめてみましょう。
- 冒頭からつい士業側の自己主張をしてしまいがちですが、これはいったん置いておきます。
- 主張より先に、まずは訪問者との関係構築が優先です。
- そして関係構築のためには、冒頭や中間で合致感や共感を得てもらう必要があります。
- 合致感、共感を得られた後、環境が整ってから初めて自己主張です。
この流れを意識しておくほど、直帰率(ウェブサイトを訪問後、そのまますぐ帰ってしまう)や離脱率(最終的なゴールまで到達せず、ウェブサイト外に離脱してしまう)の低いウェブサイトを作りやすくなります。
まずはパターンに当てはめてコンテンツの流れを作ってみよう
コンテンツ配置のおすすめパターンについて、上記の流れで考えやすいようにPDFファイルを用意しました。
1枚目が一般的な例、二枚目が空欄になっていますので、これから士業ウェブサイト(特に業務特化型)を作るご予定の方は、各段階ごと貴事務所の内容を当てはめて、導入や共感の強いパターンを検討してみてください。
開業直後など集客のイメージが湧きにくい時期ほど、このパターンをベースにしてウェブサイトを作ると迷子にならず済むのでオススメです。
関連性の高い記事
IWAMOTO
最新記事 by IWAMOTO (全て見る)
- 2024年G. W.期間中の休業日について - 2024年4月26日
- 【制作事例】東京都世田谷区の法律事務所様(総合サイト) - 2023年11月13日
- 【制作事例】宮城県仙台市の税理士法人様(総合サイト) - 2023年11月13日